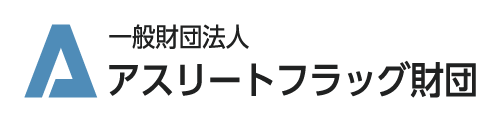為末大さん インタビュー
社会に求められる新しいアスリートの形「ワンアスリート・ワンイシュー」
2020/02/05
現役時代は陸上選手だった為末大氏は、世界陸上選手権の男子400mハードルで銅メダルを獲得するなど、日本陸上史に名を残すアスリートだった。現役引退後はさまざま形で多くの事業に参画し、セカンドキャリアにおいても成功を収めている。アスリートとビジネスパーソンという2つの顔を持つ為末氏が、自身の経験からアスリートのあり方について語る。
(文・構成=久我智也、写真=高橋学)
活動資金の集め方「応援対象を自分からビジョンへと変える時代に」
――為末さんは法政大学卒業後に大阪ガスに入社されましたが、1年半ほどで退社してプロ宣言をされました。当時はどのような形で活動資金を集められたのでしょうか?
為末 基本的には、大会賞金とスポンサーからの援助が主な資金となっていました。レースの賞金は年間で約300〜600万円ほど。それに加え、スポンサーからの支援をいただいていました。年間の活動費は、ぜいたくをしなければ500〜600万円ほどだったと思います。
スポンサー探しはマネージメント事務所がしてくれていたので、そのスポンサー候補に会いに行くのが僕の主な活動でした。とはいえ、会えばすぐに支援いただけるわけでもなく、断られることも多々ありました。企業からすると、広告目的の場合は一部の超有名アスリートを除いてアスリートに投資する経済合理性はないんです。僕も知名度はあまり高くなかったので、別のロジックでバリューを提供してスポンサードを得ようとしていました。
――別のロジックとはどのようなものでしょうか?
為末 たとえば、インナーコミュニケーションへの貢献です。企業のイベントに参加して社員の方々のモチベーションアップへの貢献、採用活動への協力、スポンサーの得意先企業に会いに行くということもありました。
――自身が持つソフトパワーを生かして、スポンサーを獲得していったのですね。
為末 そうですね。アスリートやスポーツが持つソフトパワーはとても強いものだと思っていますから、教育や地域活性化といった社会課題の解決にも貢献できるはずです。ただ、今のスポーツ界はそのソフトパワーをまだまだ上手に活用できていません。良い例とは言い難いですが、ヒトラーはスポーツとナショナリズムをかけ合わせて徹底的に国威発揚に活用しましたが、スポーツに何かを込めると強力な増幅装置になるんです。そういったように“スポーツに何を入れるか”を考えていくと、社会課題に良い影響を及ぼしていくと思っています。
最近では個々のアスリートが「僕を応援してください」ではなく、「僕は社会のこういう課題を解決したいから、一緒に応援してくれませんか」というように、応援の対象を自分からビジョンへと変え、それによって資金や力を結集する事例も増えていますよね。この形の支援は長続きしやすいですし、社会に良い影響を及ぼすものなので、とても良いと思っています。
――これからのアスリートは、競技以外の面でも世の中に貢献していかなくてはならないということですね。
為末 とはいえ、ひとりのアスリートがすべての社会課題を解決できるわけではないので、ひとりのアスリートがひとつのイシューにコミットしていく、「ワンアスリート・ワンイシュー」の形がいいのではないかと思っています。特に、アスリート自身と社会課題がセットになっていて、「なぜこのアスリートがこの課題に取り組むのか」という必然性を感じられる組み合わせだと、応援もしやすくなりますよね。
アスリートがセカンドキャリアを構築するうえで抱える2つの課題とは?
――為末さんはアスリートのセカンドキャリア支援にも取り組まれていますが、そこにはどのような課題があるのでしょうか?
為末 大きく2つの課題があると思っています。1つはスキルです。アスリートのほとんどは学生時代から競技だけをやってきているので、一般企業や社会で使えるスキルが身についていません。そのような状況で、引退後に食っていけるかどうかわからないという悩みを持っているんです。しかも、多くのアスリートは競技中心の人間関係なので、引退後のキャリアを考える上で十分なアドバイスも得られないんです。数少ない競技外の知人を頼った結果、「この仕事は自分のやりたいことではない」「自分には合っていない」と感じて、再び新たな道を探らなくてはならないというケースも多いのです。ただ、この課題は引退後にいろいろな人の話を聞いたり、自分自身で勉強する時間的余裕、それを可能にする金銭的な余裕があったりすれば、かなり解消されるかなと思っています。
もう1つは、アイデンティに関する課題です。競技以上に打ち込めるものを見つけられず、第二の人生で何をすべきか苦しんでしまうというものです。競技に集中していた人、高みに上り詰めた人ほど感じるもので、ある種でぜいたくな悩みとも言えます。ですが、そうした人のほとんどが数年間は生活に困らないくらいの蓄えもある人が多いです。その分だけ悩みも深くなってしまうことがあるんです。この悩みに対しては、「引退後に何をやろう」と考えるのではなくて、「競技を通じて自分は何をやりたいと思っていたのか」という問いかけが重要です。人によっていろいろな答えが出てきますが、次に「それは他の方法では手に入らないものなのか?」と問うと、案外と他のやり方が見つかり、それがセカンドキャリアにつながっていきます。つまり、目指すべき山頂は現役時代と同じであれば、今度は違う登り方をしてみませんかと促してみるんです。
――為末さんの場合は、競技を通じて何をやりたいと考えていたのでしょうか?
為末 「自分はどこまで行けるのか」が現役時代のテーマでした。引退後は主語を変えて、「人間はどこまで伸びることができるのか」をテーマにしています。山頂は同じなので、現役時代と共通点の多い取り組みができていると思っています。
アスリートはとてもコンペティティブな状況に置かれるので、本質的には人の応援なんてしないんです。少なくとも、僕は一度もしませんでした。でも、引退して数年してから、ようやく自分以外の人間が主役になることに対して心底応援できるようになっていきました。だから、現在はスポーツ領域やメディカル・ヘルスケア領域の企業をサポートしたり、子どもたちにランニングを教えたりといった形で、人間の可能性を広げるサポートをしていて、大きなやり甲斐を感じています。
スポーツはたくさんの人が少しずつ支える世界に変化「社会にとって必要だと思われる選手に」
――アスリートフラッグ財団はスポーツギフティングサービスでアスリートの支援を行い、究極的にはアスリートが活動資金に不安を感じなくてすむような世界をつくりたいと考えています。もしも、そのような世界が訪れたとき、日本のスポーツ界はどう変わっていくと思われますか?
為末 選手たちは、“良いこと”をし始めるようになるのではないでしょうか。仮に、アスリートフラッグ財団が目指す世界が訪れたとしても、全員が全員そうなるわけではありません。応援したい、応援する価値がある、言い換えれば社会に対して良いことをしている選手、社会にとって必要だと思われる選手にお金が集まるようになっていくと思います。現在のスポーツは特定の個人や企業が大金を投じて支えているような状況ですが、これからはたくさんの人が少しずつ支える世界になっていくと思います。その意味でも、より多くの人に共感されるビジョンを持ったアスリートが多く生まれてくるのではないでしょうか。
――お金を集めることができても、その使いみちに困ってしまうようなアスリートもいるかと思います。そうしたアスリートに対してアドバイスはありますか。
為末 お金をもらう意味をかみ締めてもらいたいとは思いますね。お金は人と人をつなぐパイプのようなものですよね。いかにも日本人っぽい表現かもしれないですが、何が“野暮”で、何が“粋”かをちゃんと考えたうえで活動してもらいたいと思いますね。
アスリートフラッグ財団では、アスリートの皆様のスポーツギフティングサービス「Unlim」へのご登録を受け付けています。ご希望のアスリート・スポーツ団体の皆様は、以下からお申し込みください。